NEWS
7月19日(土)来校型オープンキャンパスにて行われる『授業体験』の予告編をお届けします。
実際に大学で行われている授業を50分間に凝縮し、大学での学びを体感できます。
駿河台大学オープンキャンパスで、あなたに合った学びを見つけてください!
※7月19日(土)、20日(日)は午前と午後の2回、授業体験を実施します。詳細はオープンキャンパスページ、タイムテーブルをご覧ください
実際に大学で行われている授業を50分間に凝縮し、大学での学びを体感できます。
駿河台大学オープンキャンパスで、あなたに合った学びを見つけてください!
※7月19日(土)、20日(日)は午前と午後の2回、授業体験を実施します。詳細はオープンキャンパスページ、タイムテーブルをご覧ください
法学部
午前・午後

「酔っていて、覚えていません」は、罪を免れる理由になるの?
担当:長谷川 裕寿
記憶にございません…
いわゆる名門と評される高校・大学を出た「政治家先生」たちが、法的責任・政治的責任を追及されそうになると、一時的な記憶喪失になってしまう。何とも見苦しい(聞き苦しい)ものですね。
では、これと双璧をなす言い訳、
酔っていたので…
との言い訳はどうでしょうか。正直、「だからどうした!」とのツッコミで、カタのつきそうなチープな言い訳ですが、法的責任を追及するにあたって、酩酊(めいてい:酔い)を考慮しなければならないのか。考慮しなければならないとしてどうのように考慮すべきなのかの解決は、私たちが思うほど簡単ではありません。
卑近なところでも、著名人が泥酔して、隣家のトイレを拝借し、住居侵入罪で捜査されるというお粗末な事件が発生しました。どうやら泥酔は免責の理由にはならないようです。では、どうしてでしょうか。その根本を一緒に考えてみましょう。
担当:長谷川 裕寿
記憶にございません…
いわゆる名門と評される高校・大学を出た「政治家先生」たちが、法的責任・政治的責任を追及されそうになると、一時的な記憶喪失になってしまう。何とも見苦しい(聞き苦しい)ものですね。
では、これと双璧をなす言い訳、
酔っていたので…
との言い訳はどうでしょうか。正直、「だからどうした!」とのツッコミで、カタのつきそうなチープな言い訳ですが、法的責任を追及するにあたって、酩酊(めいてい:酔い)を考慮しなければならないのか。考慮しなければならないとしてどうのように考慮すべきなのかの解決は、私たちが思うほど簡単ではありません。
卑近なところでも、著名人が泥酔して、隣家のトイレを拝借し、住居侵入罪で捜査されるというお粗末な事件が発生しました。どうやら泥酔は免責の理由にはならないようです。では、どうしてでしょうか。その根本を一緒に考えてみましょう。
経済経営学部
午前

ホテルのホスピタリティの最前線
~ラグジュアリーホテルの元マネジャーが語る舞台裏~
担当:式場 朝夫
いきなり問題です。100-1=?いくつでしょうか?これは私自身がホテルの最前線で長年指揮をとる中で、肝に銘じてきた「方程式」なんですよ。ここには実はホテルのホスピタリティの真実が凝縮されています。答えは模擬授業の中で紹介しますね!
ファイブスターと称されるようなラグジュアリーホテルでは、優雅で洗練された空気の中にも穏やかな笑顔と温かくきめ細やかな心配りが感じられるホスピタリティに、時には感動を覚えることもあります。お客様の心を掴んで離さないそのプロフェッショナルな対応はどの様にして生まれるのでしょうか?
その舞台裏には、最高のサービスが自然と「湧き上がる」経営のしくみや働きかけ=マネジメントがあります。いまホスピタリティの最前線ではどのような取り組みが行われているのか、ホテルの新人トレーニングのプチ体験も交えながら、世界中のトップレベルのラグジュアリーホテルが目指すホスピタリティのポイントまでお話しします。
担当:式場 朝夫
いきなり問題です。100-1=?いくつでしょうか?これは私自身がホテルの最前線で長年指揮をとる中で、肝に銘じてきた「方程式」なんですよ。ここには実はホテルのホスピタリティの真実が凝縮されています。答えは模擬授業の中で紹介しますね!
ファイブスターと称されるようなラグジュアリーホテルでは、優雅で洗練された空気の中にも穏やかな笑顔と温かくきめ細やかな心配りが感じられるホスピタリティに、時には感動を覚えることもあります。お客様の心を掴んで離さないそのプロフェッショナルな対応はどの様にして生まれるのでしょうか?
その舞台裏には、最高のサービスが自然と「湧き上がる」経営のしくみや働きかけ=マネジメントがあります。いまホスピタリティの最前線ではどのような取り組みが行われているのか、ホテルの新人トレーニングのプチ体験も交えながら、世界中のトップレベルのラグジュアリーホテルが目指すホスピタリティのポイントまでお話しします。
午後

食のインフレ
~ファストフードが贅沢品になる未来がくる?~
担当:石川 清貴
昨今、世界的にファストフードの値上げが相次いでいます。日本のマクドナルドでは、2023年から値上げが相次ぎ、また都心部の店舗ではさらにプラス10円~50円ほどの上乗せがありました。「安い」ことがファストフードの魅力の一つでしたが、いずれ庶民には手が出せない食べ物になるかもしれません。実際、アメリカの一部の州では、ビッグマックのセットが18ドル(日本円で2700円ほど)で売られています。しかし、値上げの結果、客足が遠のいたわけではありません。日本マクドナルドでは、値上げ後においても、売上高は前年同期比で伸びています。
ファストフード業界に何が起こっているのでしょうか? ヒントは他の飲食サービスにはない独自のビジネスモデルにあります。企業の価格決定に影響を与えるさまざまな要因を経済学のツールを使って一緒に考えていきましょう。
担当:石川 清貴
昨今、世界的にファストフードの値上げが相次いでいます。日本のマクドナルドでは、2023年から値上げが相次ぎ、また都心部の店舗ではさらにプラス10円~50円ほどの上乗せがありました。「安い」ことがファストフードの魅力の一つでしたが、いずれ庶民には手が出せない食べ物になるかもしれません。実際、アメリカの一部の州では、ビッグマックのセットが18ドル(日本円で2700円ほど)で売られています。しかし、値上げの結果、客足が遠のいたわけではありません。日本マクドナルドでは、値上げ後においても、売上高は前年同期比で伸びています。
ファストフード業界に何が起こっているのでしょうか? ヒントは他の飲食サービスにはない独自のビジネスモデルにあります。企業の価格決定に影響を与えるさまざまな要因を経済学のツールを使って一緒に考えていきましょう。
メディア情報学部
午前
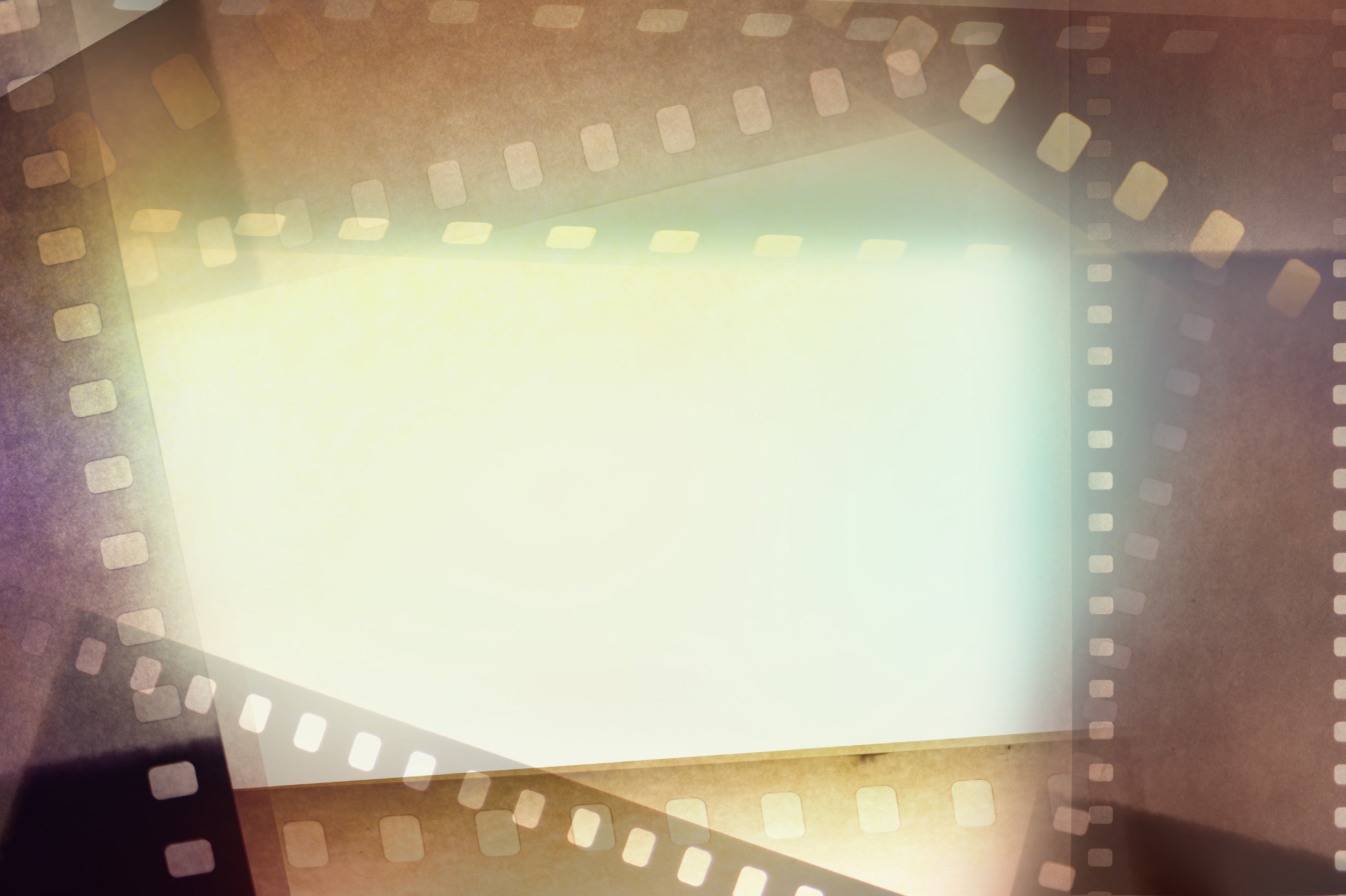
印象ががらりと変わる「映像編集」のふしぎ
〜トリック映画からサスペンス映画まで〜
担当:小川 真理子
世界ではじめてのトリック映画は、いつ頃つくられたと思いますか?
答えは、いまからおよそ130年前です。当時の人々は、まるでマジックのようだとその不思議の世界に引きつけられました。このマジックの種明かしは、「編集」です。この時代から10年後… “同じ時間に違う場所で起きているできごと”(どんなできごとかな?想像してくださいね)を見せて観客をドキドキさせる映像技術が生まれました。これもまた「編集」です。そして、サスペンス—観客の気持ちを宙吊り状態にすること—の効果を与えるものとして、現在ではおなじみです。
編集は、つくり手たちがその時代を映像にきざみ込むために工夫をしてきた、映像だけが持つ特別な技術だとも言われています。皆さんも、授業で映像の歴史を振り返りながら、普段何気なく見ている映像編集を体験してドキドキしてみませんか。普段やっているスマホでの映像編集に、少しだけ意識して取り入れてみると楽しいですよ!
担当:小川 真理子
世界ではじめてのトリック映画は、いつ頃つくられたと思いますか?
答えは、いまからおよそ130年前です。当時の人々は、まるでマジックのようだとその不思議の世界に引きつけられました。このマジックの種明かしは、「編集」です。この時代から10年後… “同じ時間に違う場所で起きているできごと”(どんなできごとかな?想像してくださいね)を見せて観客をドキドキさせる映像技術が生まれました。これもまた「編集」です。そして、サスペンス—観客の気持ちを宙吊り状態にすること—の効果を与えるものとして、現在ではおなじみです。
編集は、つくり手たちがその時代を映像にきざみ込むために工夫をしてきた、映像だけが持つ特別な技術だとも言われています。皆さんも、授業で映像の歴史を振り返りながら、普段何気なく見ている映像編集を体験してドキドキしてみませんか。普段やっているスマホでの映像編集に、少しだけ意識して取り入れてみると楽しいですよ!
午後

どうしてフェイクニュースを信じてしまうの?
~AIが作成するフェイクニュースと様々なバイアス~
担当:舘 秀典
近年の生成AI技術の発達により、誰もが簡単な操作で本物と見紛う写真や動画、文章を生成できる時代となりました。
生成AIの問題は、映像、音楽、デザイン、イラストなど多岐にわたっており、既にソーシャルメディア、WebなどにおいてAI技術を用いて生成された情報が多く掲載され、社会的にも影響を及ぼしています。
なぜ人はフェイクニュースを信じてしまうのか。AIが作成した記事を見ながら特徴を見出してみましょう。
また、AIが生成するデータに影響するさまざまなバイアスについて理解し、メディアリテラシーと批判的思考力を高め、情報の信憑性を判断する能力を向上させるにはどうしたらよいか考えてみましょう。
~AIが作成するフェイクニュースと様々なバイアス~
担当:舘 秀典
近年の生成AI技術の発達により、誰もが簡単な操作で本物と見紛う写真や動画、文章を生成できる時代となりました。
生成AIの問題は、映像、音楽、デザイン、イラストなど多岐にわたっており、既にソーシャルメディア、WebなどにおいてAI技術を用いて生成された情報が多く掲載され、社会的にも影響を及ぼしています。
なぜ人はフェイクニュースを信じてしまうのか。AIが作成した記事を見ながら特徴を見出してみましょう。
また、AIが生成するデータに影響するさまざまなバイアスについて理解し、メディアリテラシーと批判的思考力を高め、情報の信憑性を判断する能力を向上させるにはどうしたらよいか考えてみましょう。
スポーツ科学部
午前

性の多様性とスポーツの平等性を考える
担当:乗松 優
1989年にデンマークで、事実上の同性婚制度である登録パートナーシップ制度が誕生して以来、国際社会では法的に同性パートナーの婚姻関係を認める国が増えてきました。日本でも、2015年に渋谷区と世田谷区が同性カップルにパートナーシップ証明書を発行するなど、様々な性のあり方が尊重されつつあります。
こうした変化はスポーツの世界にも及んでいます。今日、トランスジェンダー選手と呼ばれる人たちが注目されるようになりました。性自認や性表現が生まれ持った性別と一致しない選手に対して、スポーツ参加の門戸が開かれたのです。しかしながら、男性として生まれ、女性としてのアイデンティティを持つ選手が女子競技に参加しても良いのか、その是非が問われるようになりました。
果たして、性の多様性を認めながら、スポーツの平等性を保つことはできるのでしょうか。今、私たちが目にしているのは、男性と女性という二分化された競技のあり方を問い直す出来事です。模擬授業では、スポーツ界が直面する新たな課題について整理します。
担当:乗松 優
1989年にデンマークで、事実上の同性婚制度である登録パートナーシップ制度が誕生して以来、国際社会では法的に同性パートナーの婚姻関係を認める国が増えてきました。日本でも、2015年に渋谷区と世田谷区が同性カップルにパートナーシップ証明書を発行するなど、様々な性のあり方が尊重されつつあります。
こうした変化はスポーツの世界にも及んでいます。今日、トランスジェンダー選手と呼ばれる人たちが注目されるようになりました。性自認や性表現が生まれ持った性別と一致しない選手に対して、スポーツ参加の門戸が開かれたのです。しかしながら、男性として生まれ、女性としてのアイデンティティを持つ選手が女子競技に参加しても良いのか、その是非が問われるようになりました。
果たして、性の多様性を認めながら、スポーツの平等性を保つことはできるのでしょうか。今、私たちが目にしているのは、男性と女性という二分化された競技のあり方を問い直す出来事です。模擬授業では、スポーツ界が直面する新たな課題について整理します。
午後

自分の身体を知ろう~発育期の身体とスポーツ~
担当:飯田 悠佳子
あなたの身体は"かたい"ですか?それとも"やわらかい"でしょうか?
そもそも"身体がかたい"ってどういうことでしょうか?
"身体のかたさ"は、スポーツでのパフォーマンス発揮や、ケガのしやすさなどと関わりが深いことが知られています。
そして、この"身体のかたさ"には個人差があり、発育とともに変化することもわかっています。
この模擬授業では、その仕組みを解説するとともに、"身体のかたさ"をチェックする方法を紹介します。
自分の身体の特徴を知ることで、安全に楽しくスポーツを続けていくにはどうしたら良いかを一緒に考えてみましょう。
担当:飯田 悠佳子
あなたの身体は"かたい"ですか?それとも"やわらかい"でしょうか?
そもそも"身体がかたい"ってどういうことでしょうか?
"身体のかたさ"は、スポーツでのパフォーマンス発揮や、ケガのしやすさなどと関わりが深いことが知られています。
そして、この"身体のかたさ"には個人差があり、発育とともに変化することもわかっています。
この模擬授業では、その仕組みを解説するとともに、"身体のかたさ"をチェックする方法を紹介します。
自分の身体の特徴を知ることで、安全に楽しくスポーツを続けていくにはどうしたら良いかを一緒に考えてみましょう。
心理学部
午前・午後
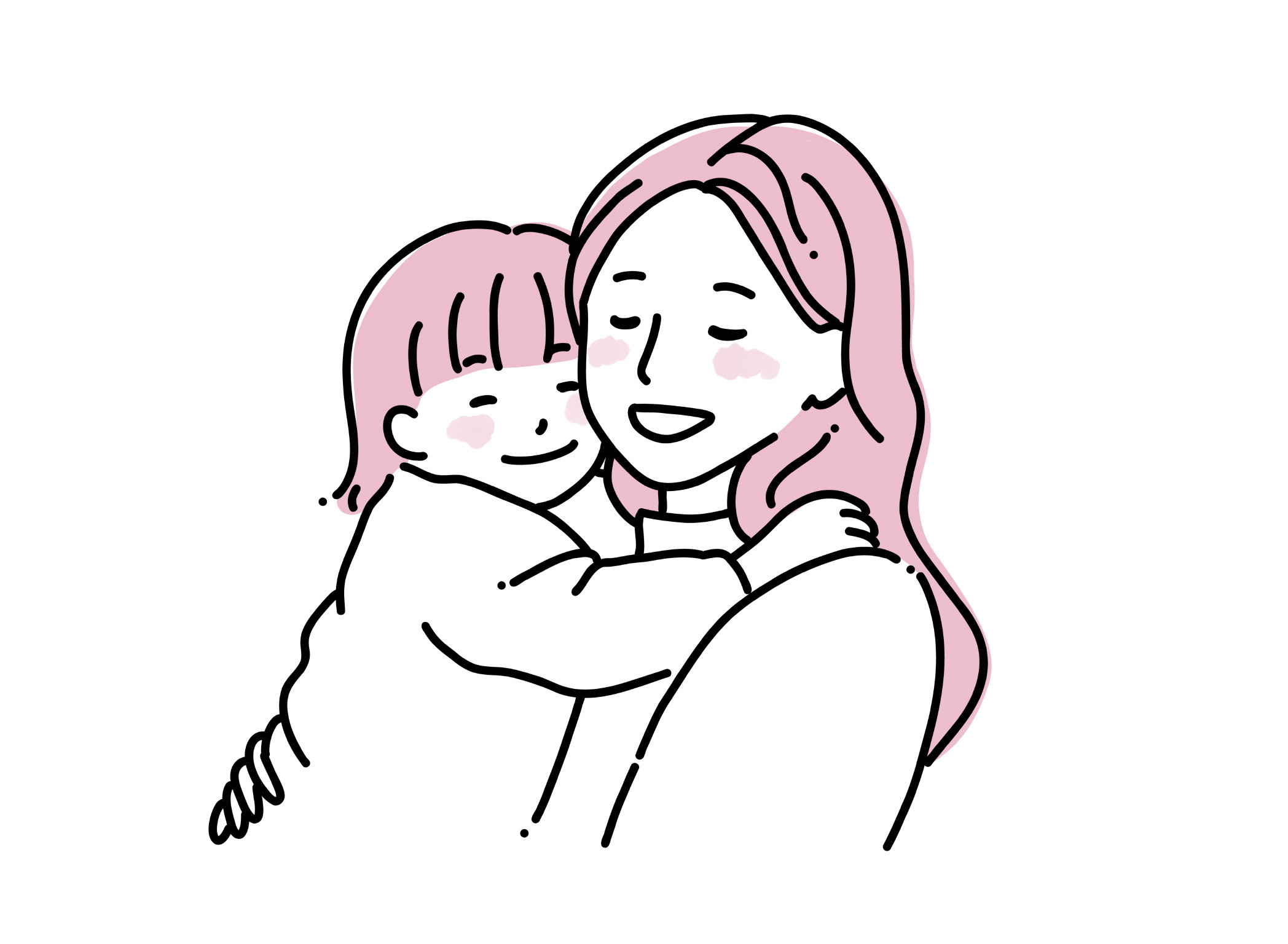
「くっつきたい」傾向から探るこころの発達
~発達臨床心理学入門~
担当:相馬 花恵
皆さんは、どんなときに「(ほかの人やモノに)くっつきたい」と思いますか?たとえば、不安や緊張でなかなか眠れない夜などは、人恋しくて誰かのそばにいたいと思ったり、手触りの良いクッションをぎゅっと抱きしめたくなったり…そんな経験がある人もいるかもしれません。
この授業では、人が本来持っている「くっつきたい」傾向=アタッチメントについてお話をします。アタッチメントは、人のこころの健康を理解・支援するうえで、欠かせない概念の一つです。
これまでの心理学研究から、乳幼児期の段階から、くっつき方(不安な時に身近な大人に対してどのように近接を求めるか)には個人差がみられることがわかっています。この個人差を、心理学ではアタッチメントタイプといいます。授業ではそれぞれのタイプの特徴について、動画を見ながら解説するとともに、安定したアタッチメントを育むための心理学的支援についてもお話します。
担当:相馬 花恵
皆さんは、どんなときに「(ほかの人やモノに)くっつきたい」と思いますか?たとえば、不安や緊張でなかなか眠れない夜などは、人恋しくて誰かのそばにいたいと思ったり、手触りの良いクッションをぎゅっと抱きしめたくなったり…そんな経験がある人もいるかもしれません。
この授業では、人が本来持っている「くっつきたい」傾向=アタッチメントについてお話をします。アタッチメントは、人のこころの健康を理解・支援するうえで、欠かせない概念の一つです。
これまでの心理学研究から、乳幼児期の段階から、くっつき方(不安な時に身近な大人に対してどのように近接を求めるか)には個人差がみられることがわかっています。この個人差を、心理学ではアタッチメントタイプといいます。授業ではそれぞれのタイプの特徴について、動画を見ながら解説するとともに、安定したアタッチメントを育むための心理学的支援についてもお話します。
