NEWS
情報処理教育センター 助教 新井 葉子
AIが裁判官になったら、という想定で繰り広げられる小説を2冊続けて読んだ。竹田人造『AI法廷の弁護士』(2024)と中山七里『有罪、とAIは告げた』(2024)。どちらも「緊迫のAIミステリ」、あるいは「半歩先のリアルを描く、リーガルミステリ!」との惹句どおりの推理小説だ。こうした物語は、AI法廷がノンフィクションとしても成立しうる世界に住む私たちに、思考実験のチャンスをも与えてくれる。
いずれの物語も、舞台は「AI裁判官が導入された日本」。そして興味深いことに、いずれの物語でもAI裁判官は外国製だ。外国製の生成AIプログラムに日本の法律や判例を学習させたコンピュータが法廷で稼働する。裁判で弁護士や検察官、証人の発言を入力され、判決を出力する仕組みだ。
中山の物語には、現実にネットに掲載されたエストニアの「ロボット裁判官」の記事が登場する。エストニア在住の大津陽子氏が2019年に執筆したものだ。多様な公的分野でAI活用を進めている同国が、AI搭載の「ロボット裁判官」の設計に取り組んでいることを紹介している。
記事掲載から5年が経過した2024年現在、プロジェクトは実現したのだろうか。調べてみると、同国では現在もロボット裁判官を導入していない。判決を導き出すまでの過程が誰の目にも明らかで、かつ論理的に説明ができなければ導入できない、という立場だ。生成AIのブラックボックス的な振る舞いが懸念されているのだ。AIがどのようなデータを参照し、どのようなプログラムに基づき判断を出すのか。ChatGPTなどの生成AIを試したことのある人なら、こちらの質問に対してAIが返してくる「まことしやかな嘘」に辟易した経験があるだろう。
今回紹介した物語は、それぞれにAI裁判官導入の利点と危うさとを描き出している。その論点も含め、生成AIを社会でどう取り入れていくべきなのか、考えさせられた。
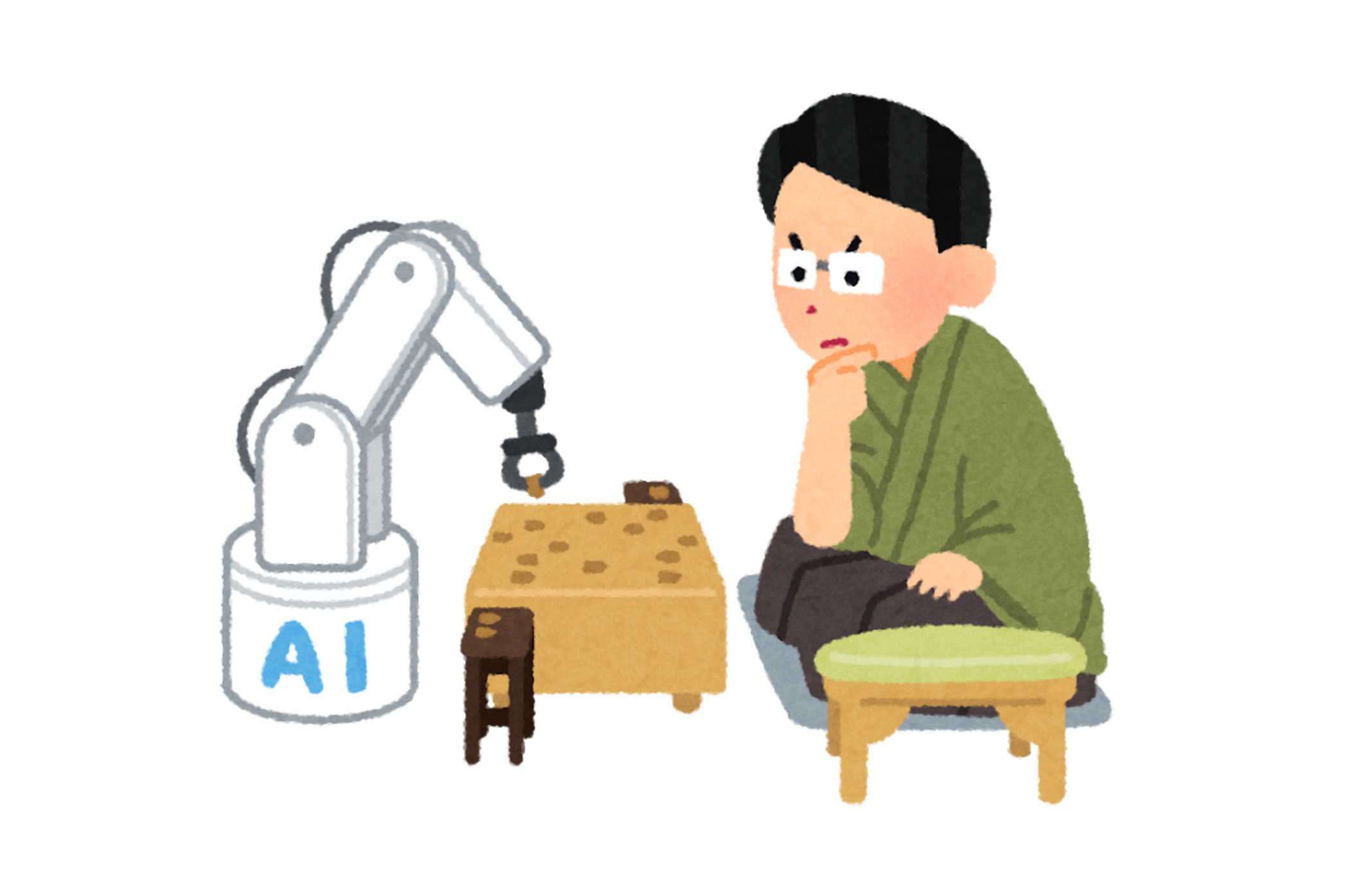 「かわいいフリー素材集 いらすとや」(https://www.irasutoya.com/)より
「かわいいフリー素材集 いらすとや」(https://www.irasutoya.com/)より「人工知能と戦う将棋の棋士のイラスト」
ひところ、チェスや将棋、囲碁の対局で名人がAIと対戦するイベントが注目を集めた。1997年にチェスの世界チャンピオンがIBM社のコンピュータ「ディープブルー」に負け、コンピュータ新時代の到来を知らしめた。棋界では2010年代にプロ棋士とコンピュータ将棋ソフトとの対決が続々と企画されたが、2016年以降は人間がコンピュータに勝てる見込みはなくなったという。その代わり、コンピュータ将棋を研究に使う若手が台頭してきた。
AIとはコンピュータ・プログラムであり、コンピュータは計算機だ。よって、数理とつながるボードゲームなどの分野でAIが人間と対決したり、AIを人間のトレーニングに利用したりすることには納得がいく。だが、裁判官に求められるのは深い見識から導き出される道徳感や正義感だ。この“感受性”の領域を計算機任せにしてしまうことは違和感がある。AIがこの先さらなる進化を遂げれば、この違和感は払拭されるのだろうか。
出典
- 竹田 人造『AI法廷の弁護士』(早川書房 2024)
- 中山 七里『有罪、とAIは告げた』(小学館 2024)
