- トップ
- 学部・研究科レポート
- 心理学部の授業『子どもと音楽』の紹介
学部・研究科レポート
子どもの心理コース科目には「子どもと音楽」という授業があります。実際に、電子ピアノを使用しながらおこなわれる、とても実践的な授業にもなっています。この記事では、授業についてご担当の木下容子先生におうかがいするとともに、実際の授業がおこなわれている様子や履修者の声もお届けしたいと思います!
-
この授業では、どのようなことが学べるのでしょうか?音楽が人間に及ぼす影響は多岐に渡ります。例えば、ある曲を聴くと特定の感情が沸き上がったりする「心理作用」、リズムの良い曲を聴くと思わず体を動かしたくなる「身体作用」、音楽が流れると、他者と関わったり一緒に演奏したくなる「社会作用」などがあります。このような音楽の機能を、子どもの発達支援にどのように役立てるかを学ぶことが出来る授業です。音楽という非言語的な媒体を用いて、子どもの発達段階に応じて柔軟に音楽要素を変化させながらアプローチしていきます。履修生には実際に音楽を体験してもらって、音楽のもつパワーを肌で感じてもらいます。

-
授業の雰囲気や履修生の様子を教えてください!子どもが好む曲を伴奏できるようにしたり、活動に合わせてアレンジできるように取り組んでいきます。1人1台のキーボードがあるため、個々人がじっくり練習し上達していっています。
またグループ演習も行っていて、各グループが大人役と子ども役に分かれて、実際の発達支援の現場を想定して音楽活動を展開していきます。実施者側の履修生は、子ども役を音楽活動に誘導し、出来たら褒めてと臨機応変に対応していきます。このように、子どもに対する支援方法を具体的に学んでいきます。
音楽とは不思議なもので、そこに音楽が流れるだけで履修生は自然と体を動かしたり、他者と活発にコミュニケートしています。毎回その場の全員が笑顔になっています!

木下先生、授業についてお教えいただき有難うございました!最後に、履修生の声もお届けします!
-
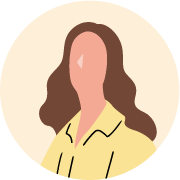
将来、子どもと関わる仕事を考えている人はもちろん、音楽に興味がある人なら誰でも楽しめる授業です!また生徒同士の話し合いや歌唱、演奏、実演などが多いため、積極性が求められます。始めは授業についていけるか心配でしたが、第1回のオリエンテーションで「他者のために自分を使い切る練習をする」という先生のお言葉に感銘を受け、自ら発言するよう努めました。この授業を受講してから、以前よりも積極的な行動を取れるようになったと思います。
-

この授業は、真面目な講義の時は真面目に、楽しい活動は賑やかな雰囲気で進み、特に子どもの身体活動についての会では、先生が弾く音楽に合わせて教室内を動き回って、とても盛り上がっています。この授業を通じて、音楽が持つ動きを引き出す力を子ども目線になって学ぶことができました。また、キーボードを弾く機会があるのですが、木下先生には優しくご指導いただき、未経験な私でも楽しく学ぶことができました。「音楽が子どもの発達にどう影響するのか」を学びたい人にオススメしたいです。
