- トップ
- 学部・研究科レポート
- 研究科の授業紹介2:臨床心理学専攻-馬場 存教授
学部・研究科レポート
精神医学特論:精神病理学に重点を置いた疾患理解と臨床実践

受講生の感想を紹介しつつ、私の講義について書かせていただきます。
-

心理師として働く上で、アセスメントの視点の1つとして精神疾患の可能性を考慮することがクライエントを理解することにつながるので、自分の臨床力を高めるという意味でも精神医学について学ぶことは有益だと思います。
心理師としてクライエントに接する時、精神疾患を念頭に置く必要があるのはいうまでもなく、多面的、客観的に判断する冷静さと、共感する温かい心が必要です。その両者を養えるよう心を砕きながら、講義を進めています。
-

精神疾患や薬についての知識をより専門的に学べるだけではなく、先生のご経験も含めて講義をしてくださるので、教科書的な知識以上により実践的な視点を持つことが出来ると思います。
-

講義では事例の検討に加え、先生の臨床でのお話を伺うことで、医療的な視点から臨床場面での実践的な支援方法を学ぶこともできます。
知識はそれだけでは意味を持ちません。知識がどう役に立ってきたのか、どう活かせるのか、臨床現場のリアリティを交えて伝わるように心がけています。
私は精神医学だけでなく音楽療法や作曲なども行っていますが、たとえば音楽作品には一音たりとも意味のない音があってはなりません。講義も同じで、意味のない語りがあってはならないと考えています。一つ一つの言葉、投げかける話題・文脈すべてが意味をもち、深みや奥行きのある解説になるよう、努めています。
-
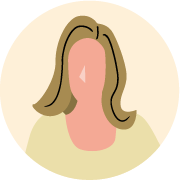
薬に関する知識や障害の発症機序、ヤスパースとシュナイダーの分類に基づいた、中核となる理論的背景などの知識とその歴史的背景や現在提唱されている仮説等の周辺知識などを学ぶことができます。
どのような理論も、歴史や背景に目を配ることが大切です。それらをたどると、一見関連のなさそうな複数の事象の根幹が実は共通していたりします。そのような学びがあると、目もくらむような膨大な情報を前にしても、全体を貫くストーリーや骨格、本質などがみえてきて「あ、そういうことか!」と腑に落ち、本質的な理解が深まってゆきます。
今、目の前にあることは、すべてさまざまな歴史を経てたどり着いた、いわば発展途上の中間地点です。賢者は歴史に学ぶといわれるように、歴史を学ばないと人間は同じ失敗を繰り返してしまいます。歴史を踏まえた学びは、より創造的な思考をもたらします。
以上、受講生の感想を元に、講義のコンセプトを一部紹介してきました。
教科書にある知識を伝達するだけなら自学で十分で、人が講義をする必要はありません。講義はいわば「ライブ」です。内容を反映した抑揚を考え、受講生の反応も踏まえて時には即興的に、臨機応変・柔軟に語ります。ただの譜面の再生でしかない音楽は意味がないのと同じように、その瞬間にしか生まれないリアリティを大切にしながら、心理師としてのスキル向上だけでなく、受講生のこれからの長い人生にも役立つよう、意義深くもわかりやすい講義をこれからも心がけていきます。


