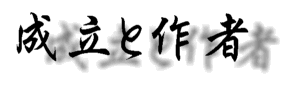
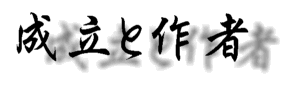
|
『とりかへばや』には、実は二種類あり、『とりかへばや』(古本)とそれを改作した『今とりかへばや』(今本)とに分けて呼ばれている。しかし現在『とりかへばや』と読んだ場合、一般的に『今とりかへばや』のことを指すことが多い。一方の古本『とりかへばや』は、散逸しており断片的に残っている資料から想像するところが多い。 なぜ古本と今本とに分かれているかは、『無名草子』の中で登場する古本と今本とが全く別の作品として紹介されているところから始まる。 古本『とりかへばや』の批評は「女中納言こそいといみじげにて、髻ゆるがして子生みたるなどよ。(中略)女中納言の死に入り、蘇へる程こそ夥しく恐ろしけれ。鏡もてきて、万のこと暗からず見たる程、まことしからぬ事どもの、いと恐ろしきまでこそ侍れ」とあるように古本では、非現実的で「恐ろしい」とか「気味悪い」という評価を受け、また物語の展開が不自然としていることからあまり好意的に受け入れられた作品ではないことが、うかがわれる。 一方の今本『とりかへばや』では、「『今とりかへばや』などの本にまさり侍るさまよ(中略)中納言の女になりかへり、子産む程の有様も、尚侍の男になる程も、これはいとよくこそあれ」のように古本の「醜悪さ」や物語りの展開の仕方などの欠点が克服されているとして評価された。その背景には、今本が『源氏物語』『浜松中納言物語』『夜の寝覚』『狭衣物語』の影響を強く受けつつ、女主人公の心理描写など、現実性を重視したことがあるだろう。 古本の大幅な改変により、題は『とりかへばや』なのに以前の『とりかへばや』とは大きく異なり、それを区別するために「今」と付けたと推測される。 『とりかへばや』の正確な成立は不明であるが、古本の成立は大体11世紀末頃と推測され、また今本の成立は大体12世紀末頃と推測されている。また作者も同様に双方とも不明で、古本の作者は物語の内容から男ではないかと推測され、今本では、「女の物語」という要素が強いことから、女性ではないかと推測されている。
参考文献: 友久武文・西本寮子『中世王朝物語全集12とりかへばや』(笹間書院) 今井卓爾『物語文學史の研究』(早稲田大学出版部) 『堤中納言物語 とりかへばや物語』新日本古典文学大系26(岩波書店) 富倉徳次郎『無名草子評解』(有精堂) |