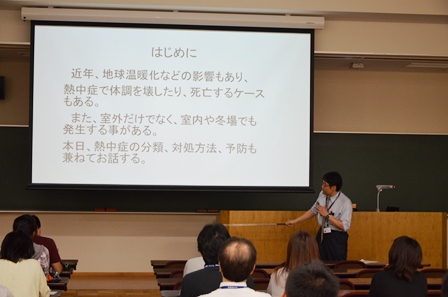2015年7月アーカイブ
7月24日(金)に交換留学生、一般留学生が学生寮フロンティアタワーズの茶室にて茶道を体験しました。
学生の中には一度茶道を体験したことのある学生、和室に入るのも初めてという学生もいました。茶室に入ると、正座をし、姿勢を正し、茶道の変遷、日本への伝来、茶室の説明、茶道具の名称や作法を学びました。ほとんどの学生が茶道ではどのようなことをするのかを知っている様子でしたが、説明を受けると、深くうなずき、茶道への理解が深まっているようでした。
次に実際に抹茶を点てました。茶筅を持ち、手首を上下に動かしお茶を点てようとするも、慣れない所作に悪戦苦闘しました。しかし、隣の人の手の動きを学び、回数を重ねるごとに上達し、とても美味しい抹茶ができあがりました。
体験のあとには、「お茶の正しい作法を知ることができ、とても勉強になった。」「苦いと思っていたお茶だが美味しく飲むことができた。」という感想が聞け、また一つ留学生の日本文化への理解が深まった機会となりました。


4月25日(土)に大地震の被害にみまわれた故郷ネパールの状況を心配しながら、勉学に勤しんでいるネパール出身の留学生に対し、7月28日(火)本部管理棟7階会議室にて、大貫秀明副学長(学生支援担当)から激励の言葉ならびにささやかな勉学補助費が贈られました。
今回の大地震は、ネパール及びその周辺国に甚大な被害をもたらし、本学では、被災地の一日も早い復旧・復興を祈り、災害支援募金も行いました。
本学のネパール出身留学生(5名)のご家族は、幸い、全員無事で自宅(実家)の倒壊等もなかったとの事です。
大貫副学長は、「ネパールの被災状況のニュースが最近少なくなってきている中、故郷への心配が絶えないと思いますが、今後も、勉強を含め是非頑張ってください」と励ましました。


ネパール出身学生のみなさん 大貫副学長(左)と木村学生支援部長(右)と一緒に
7月17日(金)に着付けの先生をお招きし、浴衣の体験を行いました。
着付け体験には交換留学生を始め、一般留学生や日本人学生あわせて15名の学生が参加しました。
まず初めに、自分の好みの浴衣と帯を選びました。女性であれば経験があると思いますが、自分の好みの色と、似合う色は別です。また、身長によっても浴衣の絵柄の見えかたが異なります。それぞれ着付けの先生にアドバイスされながらお気に入りの一着を選びました。
参加した学生は、今回初めて浴衣を着るという人ばかりでした。先生に指示をされながら腕を上げ、向きを変え、緊張した表情で着付けは始まりましたが、鏡に映る姿が美しく変化していくと、皆だんだんと笑顔になっていきました。これも女性であれば味わったことのある感覚だと思います。見慣れた姿は美しく変身し、まるで別人のように思えます。さらに着付けをしてもらっている間、その時間は自分だけに向けられたものであり、日常では味わうことのできないある種特別な雰囲気を楽しむことができます。
仕上げの帯もひとりひとり異なる形を作ってもらいました。蝶やリボン、歩く振動でピョンピョンと揺れる帯を作ってもらった学生もいました。着付けが終わると、皆外に出かけ写真を撮りました。所属するサークルの部屋へ行き披露する学生、お世話になっている先生に見せにいく学生もいました。
また、着付け方を動画で撮ったり、個人的に帯の作り方を教わる学生もおり、浴衣に対する興味の深さが伺えました。最後には「とても楽しかった!」「もう少し着ていたい」という声が聞こえ、良い体験になった様子でした。


7月16日(木)大学会館4Fにて国際交流委員会主催による夏期国際交流パーティーが開催されました。今回のパーティーでは、9月からオーストラリア、フランスへ長期留学をする学生の壮行会、9月で一年間の留学期間を終える、中国・聊城(リャオチョン)大学の交換留学生の送別会、夏休みに海外語学演習へ参加する学生の決起会が行われました。
長期留学へ出発する学生は、語学力やコミュニケーション力の向上、自己の残余との出会いによる自身の成長など、様々な目的や目標を語り、これからやってくる新たな生活や経験を楽しみにしている様子でした。留学中はいろいろなことがあると思います。そのひとつひとつと真剣に向き合い、乗り越え、自分自身を高めてほしいと思います。

海外語学演習へ参加する学生は、留学先の言語で挨拶を行いました。留学先では、美術館に行きたい、おいしいスイーツを食べたいなど、パーティーに参加している人に伝わるよう、フリップや写真を使用しながら意気込みを話しました。
夏休みを利用した短い期間の留学ではありますが、感受性が豊かな時期に多くの刺激を受け、経験するすべてを自分の力につなげてほしいと思います。

途中、春季国際交流パーティーにもご出席いただきました飯能市国際交流協会の皆様を代表して、市川会長よりご挨拶を賜りました。飯能市国際交流協会の皆様には、「飯能しゃべり場」や様々な催し事を通し、本学の留学生がお世話になっております。今後も飯能市の国際交流活動の進展に大きく寄与することができればと思います。

パーティーの最後には、9月で一年間の留学期間を終える中国・聊城(リャオチョン)大学の交換留学生が、この一年間を振り返った感想を話しました。
日本に来る以前は、「人生は自分のものであるから、自分の好きなように楽しむ。」と考えていたひとりの留学生。異国で生活する中で多数の困難と直面した時、日本人の優しさや協調性に触れ、人はひとりでは生きることはできず、協力し合うことがいかに大切であるかを知ったと話しました。
また、日本で知り合った友人や先生が、親身になり自分と向き合ってくれたことや、他の人間に対し尽力する日本人から大きな影響を受け、自分も人と真剣に向き合うようになったと話しました。
環境の異なる場所で生活することによって様々な体験や経験をした留学生。それぞれが感じた思いを忘れることなく、これからも飛躍していくことを期待しています。

本学では、平成23年度から、教育・研究・社会貢献活動等において顕著な業績を挙げた専任教員に「プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー賞」を授与しています。
今年度の受賞者は、経済経営学部の伊藤雅道教授に決定し、7月23日(木)に飯能市内のホテルにて表彰式が行われました。
伊藤教授は「土壌動物の生物多様性」「動物分類学」を主な研究テーマとし、「ミミズの先生」としても知られています。2014年には、この分野の第一人者としての研究業績が評価され、「日本土壌動物学会賞」を受賞されました。伊藤教授の学内外での活動や業績が認められ、この度の受賞となりました。おめでとうございます!

伊藤教授の挨拶

左から吉田学長・伊藤教授・山﨑理事長
7月23日(木)13時35分頃より、FM NACK5「GOGOMONZ(ごごもんず)」に、本学オープンキャンパススタッフ2名(経済学部4年 杉田一誠さん、現代文化学部3年 石川千尋さん)が出演します。
落語家 三遊亭鬼丸さんと小林アナさんのコンビでお届けする生ワイド番組「GOGOMONZ」。
学生スタッフとどのような会話が繰り広げられるのか、乞うご期待ください!
FM NACK5ホームページ http://www.nack5.co.jp//

7月21日(火)日差しが厳しい季節になった飯能キャンパスにて、献血(埼玉県赤十字血液センター主催)が実施されました。今回は34名の方々に血液の採取をしていただきました。ご協力いただい方々、お立ち寄りいただいた全ての皆様に感謝を申し上げます。なお血液型の内訳はA型11名、O型10名、B型8名、AB型5名でした。
本学では、日本赤十字社の献血を推進しており、年間に4~5回ほど校内で実施しています。
次回の献血実施は10月14日(水)の予定です。引き続き皆様のご協力をお願いいたします。

私は公務員を目指しながら教職課程を履修しています。このような事をやっていると「なんでそんな事をやっているのか。」とか「どちらかに絞ればいいじゃないか。」と言われることがあります。確かに、教職課程を履修しながら公務員試験の勉強をするのはとても大変です。どっちつかずになってしまいかねません。
私は教職課程を2年次から履修したのですが、当初は、教員免許状を取得していれば、持っていない学生より余分に単位を取りながら卒業要件単位も取ったことになるので、大変なことをやり遂げたという点で、就職活動の際に有利になるのではないかと思っていました。
しかし、今は教職課程で学んでいることが公務員試験にもかなり活かせることが分かったので、日夜取り組んでいます。たとえば、教職課程の「教科に関する科目」で、私が苦手な領域を勉強することができます。公務員試験の一般教養に関わってくるところなのでとてもありがたいです。また、教職課程の履修生だった先輩の何人かが地方公務員になって教育委員会の事務局で働いているそうなので、将来、私も教育委員会の事務局の仕事に就いたとき、教職課程で学んだことが役立てられるよう頑張りたいと思っています。
最初は教職課程を就職に有利になるかなと思って履修していたのですが、今では沢山の事を学べることが分かってきました。教職課程で学んできたことを無駄にせず、自分の進む道で活かしていきたいと思っています。
7月20日(月・祝)13:20~14:50に、第2講義棟14階会議室にて、経済研究所・飯能市共催公開講演会「消費者問題-身近な事例・歴史・対応」を開催しました。講演者の原 早苗氏は、消費者庁・消費者委員会の設立準備に関与し、2009年~2013年には消費者委員会の初代事務局長として、国の消費者政策に関わって来られた方です。
講演会ではまず、国民生活センターで集約された相談事例が紹介されました。とくに、若者に多いインターネットを利用したマルチ商法や通信販売のトラブル、高齢者に多い健康食品の送り付け商法などを説明していただきました。次いで、消費者問題の発生とそれに対応する形で取られた消費者運動や法制定の歴史を解説していただきました。最後に、消費者庁・消費者委員会が作られた背景や役割を説明していただきましたが、これまで複数の省庁にまたがっていて解決が困難であった問題への対応などが円滑にできるようになったとのお話しでした。
講演会には飯能市だけでなく、さいたま市・秩父市・所沢市・入間市・狭山市・日高市などの遠方からも、多数のご来場がありました。また、本学の学生や教職員の参加もあり、大盛況となりました。消費者問題への関心の高さと消費者教育の必要を認識した講演会でした。



2015年7月17日(金)に本学の学校医である佐瀬武先生による「熱中症対策講習会」を開催しました。学生、教職員等50名程度の参加となり、皆、熱心に講師の話を聴いていました。
いざというときの対処方法や熱中症にならないための予防方法を具体的に講習していただきました。熱中症は屋外だけでなく部屋の中でも起こり、いつでも誰にでも起こり得ること、喉が渇く前に水分を補給し、こまめな水分補給を心がけることが重要です。
この講習会を機会に正しい知識を身につけ、常に熱中症予防を心がけ、いざという時には適切な対応ができるようにしていきましょう。
以下の日時に、飯能キャンパスにおいて今年度2回目の献血を行います。
献血は16歳から69歳までの人ができるボランティアです。
献血には、献血をする人の安全と、その血液を輸血する人の安全の両方を守るため、様々な基準があります。
献血をする前に、医師の問診・血圧測定・血液型事前判定・血液比重測定(貧血の心配が無いかのヘモグロビン濃度測定)を行いますので、初めての方でも安心してご協力いただけます。
【日にち】7月21日(火)
【受付時間】(午前)10:30~13:15 (午後)14:30~16:40
【会場】講義棟1階ロビー
この件に関するお問い合わせは、健康相談室まで。
<参考>
- 日本赤十字社HP 献血の手順 http://jrc.or.jp/donation/process/index.html
- 埼玉県赤十字血液センターHP http://www.saitama.bc.jrc.or.jp/
7月13日(月)に本学AVホールにて平成27年度1級・2級・スポーツ年間特待生認定式が行われ、吉田恒雄学長から特待生の皆さんに認定書が授与されました。

6月30日(火)に留学生と本学学生が一緒に七夕の飾り付けを行いました。
まず初めに、折り紙で竹に飾る飾りを作りました。留学生のなかには折紙をあまり折ったことのない人もおり、日本人学生が折り方を教えている姿が見られました。また、とても器用な留学生は星、お財布、ピアノ、椅子など様々な折紙を次々と作っていきました。
次に短冊に願いごとを書きました。これから受ける試験に合格できるように、皆が元気に過ごせるようになど、思い思いの願いを込めて書き、竹に飾りました。短冊も作る人によって様々で、竹に下げるための紐の部分に折紙で折った飾りをデコレーションし、とてもかわいい短冊を作っていました。

続いて、7月2日(木)に七夕の発表会を行いました。七夕の由来については諸説ありますが、中国の行事が日本に伝来したものだと言われています。日本の七夕の変遷、中国ではどのような七夕が行われているのか、またドイツでは七夕に似たような行事があるかなど、何人かの学生に発表してもらいました。
日本の七夕は中国の乞巧奠(きっこうでん)という行事が日本に渡り、日本の棚機津姫(たなばたつめ)の話と融合し現在の七夕となっていること、中国では、牽牛と織女の物語にちなんで、現在では恋人同士のイベントとなっていること、ドイツでは、七夕という行事はないが、「マイバウム」という健康や幸運を願う、ミュンヘンに根強く残る祭りがあることを紹介してくれました。
また、今回は発表会の司会を務めてくださった法学部 天野教授のゼミの受講生が折紙を使って彦星と織姫の折り方をレクチャーし、参加していた学生全員ですてきな作品をつくりました。


14時30分からはたこ焼きとお好み焼き作りを体験しました。
お店ではお好み焼きを焼いたことがある留学生も、材料を用意し、生地を自分で作って焼くことは初めてです。昨年から様々な料理体験をしてきた留学生は上手に包丁を使いキャベツ、シーフード、肉などを刻みました。
いざ、調理を始めようとしたとき、「たこ焼き、お好み焼き作ったことあります!」と参加していた日本人学生の声があがりました。留学生は彼らから焼き方を教わり、おいしそうなたこ焼き、お好み焼きができあがりました。留学生は、みんなで行う調理は楽しく、料理も美味しかったと感想を述べていました。